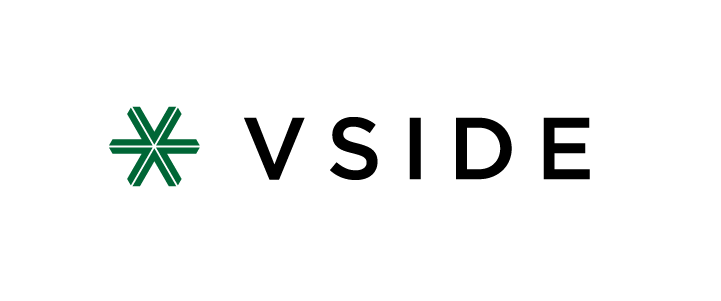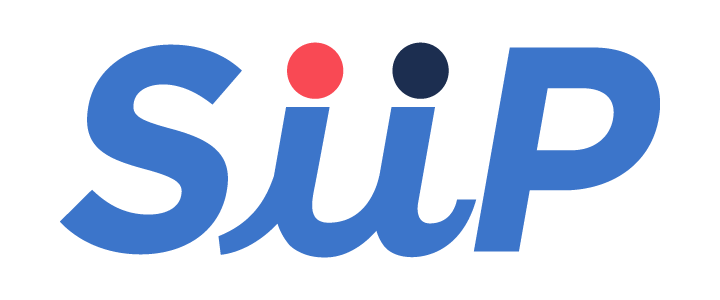2025年09月12日
壁打ち
【前編】そのアイデア、誰かに話してみた?〜起業志望者のための壁打ち活用法
起業・経営に役立つ知識
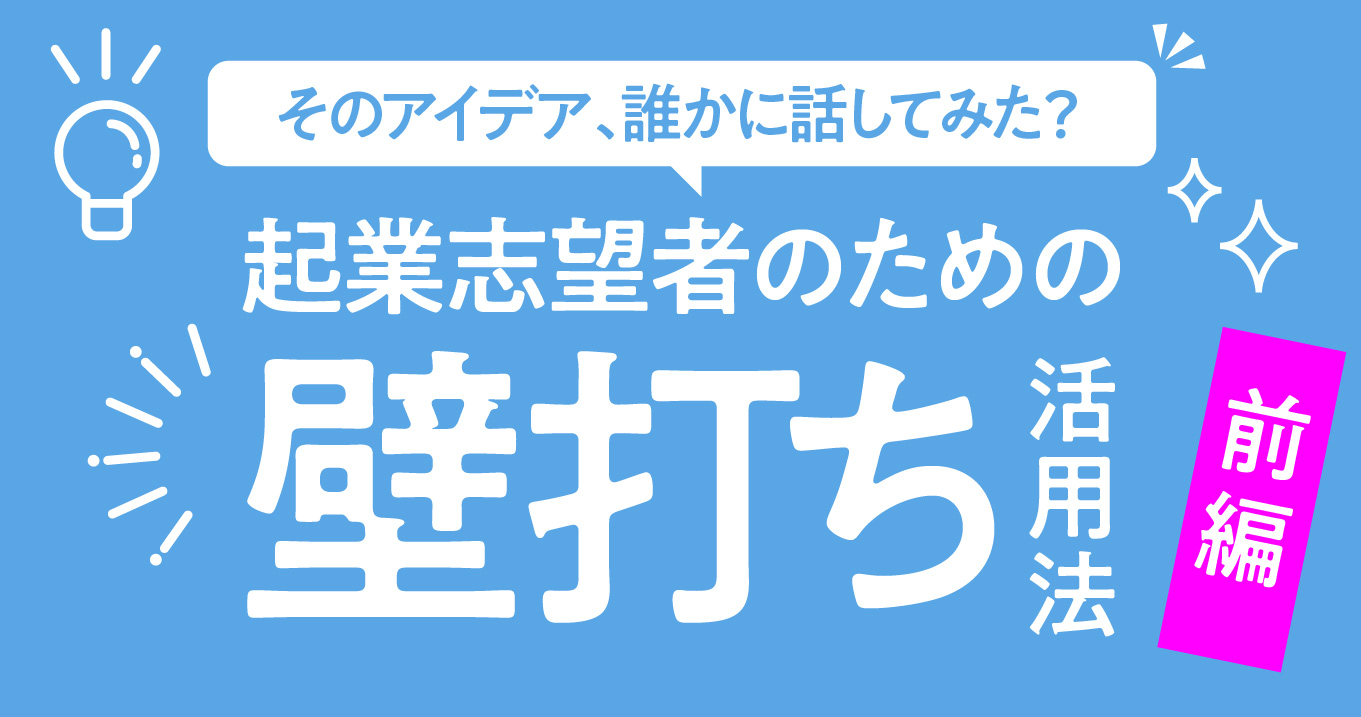
起業志望者がこれから行おうと思い描くビジネスがうまくいくかどうかは分からないものです。ではどうすればビジネスの成功率を上げ、どうすればより実現性を高められるでしょうか。
そのためには自分が持っているアイデアや考えをまずは出してみることです。その行為を私は「壁打ち」と呼んでいます。
本稿では壁打ちの重要性について述べていきます。
壁打ちとは何か?
まず、壁打ちの定義からです。
壁打ちは、一般的には「自分の考え(ここではビジネスアイデアやプラン)を人に話して整理してもらうこと」だと考えています。一方で、私は「アイデアを広げる」壁打ちもあると考えています。
ここでは深入りしませんが、あくまで「壁打ち」自体は手段です。その手段を用いてどうしたいかということですね。よって、壁打ちは「整理すること」しか行ってはいけないとか、「アイデアを広げること」しか行ってはいけないという考えは私にはありません。
今回は、壁打ちという時に、「アイデアを整理する」「アイデアをまとめて収束する」ということで一旦考えていきましょう。
壁打ちを行う際の視点
壁打ちを行うにあたって、壁打ち役側の視点だと次のようなものがあります。
- 相手はどんなビジネスをしたいのか、その進捗や状態はどうか
- 相手の意見やアイデアと、事実やデータは何か
- 相手の状況ややっていることや行動していることは何か
- 相手の心理や性格など持ち味は何か
- 相手が欲することや期待することは何か
壁打ち役は、それらを一瞬で分かるわけではありません。壁打ちという会話を通して理解を深めていくことになります。
そして相談者であるあなたに必要な視点は、次のような視点です。
- 自分はどんなことをしたいのか。このビジネスで何をしたいのだろうか
- 自分のアイデアはなんだったか。または希望や夢、今やれること、やりたいこと、できることなどごっちゃになっているのではないか
- 行動していることはあるつもりだが何をしているのか、または出来てないことはなんだろうか
- 自分の持ち味や長所や性格をうまくいかせているか、違うことをやっていないか
- 自分はなぜ壁打ちや整理をしているのだろうか
壁打ちをするときは、不安だったり、それを和らげたいという状況もありそうです。それも込みで相談されるのはいいですが、答えはあるわけでなく、答えを一緒に探す、またはヒントを得る行為だということを踏まえておかれるとよりよいと考えています。
もしかすると「壁」打ちなので、壁打ち役は相手の話をただ「ふんふん」と聞いているだけと思われるかもしれません。そうではなくて、相手の話を踏まえつつ、それに応じて適切に投げかけ、問いをしていくのが壁打ち役の役割です。
壁打ちの定義自分のビジネスアイデアやビジネスプランを考えているものを、相手(壁役)に話をしてアイデアを整理する行為。その際、壁役は相談者の意図ややりたいことを踏まえて適した問いかけや投げかけが起きている |
なぜ壁打ちが必要か?
ポイント1:主観でなく客観で見られるので、思い込みの罠を回避できる
人は思った以上に主観や思い込みに偏ります。私もそうです。あなたが良いと思っているビジネスアイデアやビジネスプランが実は既に世に出ているものであったり、成功確率が低いということは良くあります。
思い込み、バイアスを認識するには、一人ではなかなか難しいです。そこで、壁打ちをすることで、自分の思い込みを認識して、視点を広げて、成功率を高められると私は考えています。
ポイント2:未整理のアイデアが整理される
自分の考えをアウトプットし整理するということに慣れていなければ、多くは「未整理状態」の「アイデアらしきもの」を持っていることになります。ここでいう慣れている人とは、コンサルタントや講師、プランナーのようなイメージです。
頭で考えたことを何かしら言語化し、資料などにして、相手に伝えるということをしている人たちです。もちろん、独自にインプットとアウトプットを繰り返して鍛える人もいらっしゃるでしょう。
整理されていないという状態とは「うまく伝えられない」という状態や言葉で示せます。「うまく伝えられない」アイデアがあるが、それを「ビジネスとして形にできる」ことは、かなり稀であり、そういったことは少なくとも私にはありません。少なくとも「以心伝心」で伝わって勝手に整理されることはありません。
「うまく伝えられない」のに「うまくいった」とき、それは再現性もありませんし、文字通り「偶然」や「運」でしかありません。
そういう意味で、まず自分の考えやアイデアをぶつけてみる、出してみることで、その整理が促進されます。もっといえば、整理か未整理かは話してみるかはあまり分からないので、話すことで「ここは分かった」「ここが分かっていない」が明確になるというほうが分かりやすいかもしれません。
「整理」というと「簡単そう」な印象がありますが、アイデアや思考や考えを整理するのは訓練をして鍛えないと私はできないと考えています。論理もありますが、グループ化、抽象化、具体化など様々なものがあります。
ポイント3:ビジネス観点でブラッシュアップできる
ビジネスにおいては、私は4つの観点が必須だと考えています。壁打ち側によって多少の違いはあるとは思いますが、壁打ちによってこれらのビジネス観点でブラッシュアップされることが期待できます。
具体的には、
- 対象者
- 対象者の課題
- 解決策(アイデア)
- マネタイズ
の4つです。以下、それぞれ解説します。
ビジネスに必須の4つの観点
1.対象者
対象者とは、ユーザーであり、お客さんです。正確には便益を得る人です。学習塾など教育系のビジネスは、親が支払い、子どもがサービスを受けるという少し変わった形をしていますが 、この場合どちらも対象者となりそうです。スーパーなどでは地域に住んでいる生活している人たちとなりますよね。
ところで、対象者を考えていない人がいるのか?と思われるかもしれません。考えてない人は流石にいないことが多いですが、漠然としているケースは多いです。よくあるのは、仮想のペルソナ(対象とする価値観プロフィールなどをまとめた人物像)
を使うケースです。これでも場合によっては良いのですが、本当に存在しないなら意味がありません。そういう意味ではわりとこのペルソナは使い方が難しい概念だと感じています。
2.対象者の課題
対象者の課題は、文字通り、その想定するお客さんの抱える課題です。悩みや不満などと言ってもいいでしょう。これがなければ、押し付けになります。
例えば、スマートフォンケースというグッズやアイテムがありますが、これはスマホをそのまま持ち歩くと割れやすいとか傷つけるということがあったのかもしれません。その上で、さらに成熟化して色々な個性あるアイテムが出てきたと言えそうです(手帳型とか、デコで飾ったりなど)。しかし、ここで「割れやすいのが嫌」とか「傷つけたくない」とかがなければ、これらは売れないでしょう。
もしあなたが「そんな課題を取りこぼすことはありえない」と考えているならば、そういう人ほど意外にハマります。基本的なことかもしれませんが、対象者が持っている悩みではなく、憶測で「その対象者が持っているはずだ」と思い込んでいる場合も多いのです。憶測から始めるのはいいのですが、どこかで確認したいところです。
3.解決策(アイデア)
解決策とは、そのものズバリお客さんの課題をどう解決するかです。解決策があるだけで「ビジネスアイデア」になり得るとも思っています。
例えば、あなたが従業員向けの離職率を低めるアイデアを持っていて、それをSaaS型でサブスク提供していくアイデアがあったとします。このアイデアは「自社のビジョンや経営方針の理解を促す研修プログラムを用いることで、自社ロイヤリティを高める」みたいなものとします。
このアイデアが良いかどうかは分かりませんが、これが本当に、離職率を下げることに寄与するか、ということを考える必要があるわけですね。
4.マネタイズ
マネタイズは収益化、お金の取り方を意味します。実は多くのビジネスアイデアで、お客さんの財布や予算を考えず、思いつきのままであることが多いです。それこそ、色々なビジネスやビジネスモデルを知らなければ確かにここは難しい気がします。
小売であればモノを売って対価をいただく、音楽ストリーミングサービスなどは聴き放題でサブスク課金してもらうなどです。
以上、4つの観点が既にある相談者は、私の経験上、ほとんどありません。仮にあっても、それは一人では難しく、または色々と試行錯誤して得られると考えています。あっても相談者が思い込んでいるだけで違っているケースもあります。
壁打ちの際に気をつけること
壁打ちがうまくいけば未整理状態が解決されてスッキリし、やることが明確になります。ただ、それは必ず出来るわけでないでしょう。以下、壁打ちの際に気をつけたいポイントを提示します。
1.期待している点や求めている点をはっきりしておく
対人である以上、あなたが思っている成果が得られないこともあります。そうならないために、壁打ちで得たいことをなるべく明確したほうがいいでしょう。
例えば、既にアイデアはある程度あるが、対象者が本当にいるかが不安なのでそこを明確にしたい。ジャンルは決まっているが、方向性などは曖昧なのでそこを整理したい。自分の考えを聞いた上で、そのアイデアに対して意見がざっくばらんに欲しい。
これらはある種「相談」の鉄則とも言えます。受ける側視点でいえば、これらが明確ではない場合は、「お客様の期待値はなにか」をまず明確にするところから行います。そこが外れると、お互いに不幸だからですね。
2.「対象者」ではない人に意見を求めすぎない
期待値にも近いのですが、例えばラーメン好きな人向けといっているアイデアを、全くラーメンが好きでない友人に聞くなどは注意したほうがいいでしょう。
その友人が話を聞いてくれる、アドバイスをしてくれるという人であっても、その人が「欲しいかどうか」は別だからです。
いくらその友人に欲しいかを聞いても「欲しいかも」「自分は要らない」程度しか意見は出せないでしょう。
壁打ちとはあくまでも、そのビジネスアイデアを実現したりする可能性を高めるものです。友人へはアドバイスや意見はありがたいということを述べて、他の人に当たりましょう。
3.特定の人よりも複数人に聞く
一人しか聞けないなら仕方がないのですが、3人以上に聞くほうがいいでしょう。
それこそ、身内、親友、同僚、専門家など分けて、立場や価値観がある程度違うとか、狙いをずらしていくなどが考えられます。
一人ですと、その人が絶対的な立場になってしまい、壁打ちなのにその人の主観で構成されてしまいます。それは本末転倒ですから注意したいですね。
4.話を聞いてくれる人を選ぶ
稀にですが、壁打ちとして話を聞いてくれない人もいるでしょう。端的にいえば「頭ごなしに意見を言ってくる」という人です。これは壁打ち相手としては不適切なので避けましょう。
あなたは釣りが好きで、「釣り体験ツアー」を企画したいとします。これもビジネスとして自治体に売るとか、釣りメーカーとタイアップするとかそういう考えを持っていたとします。しかし、壁打ち相手が「釣りは流行らないよ」など、全く話を聞いてくれないというケースです。
話を聞いてくれるとは、あなたの意見や考えを聞いてくれる。それを踏まえた上で意見や考えを述べてくれる。そういう意味では、「YES、AND」という方ならOKです。しかし、相手の意見を「BUT」で聞かない、さえぎる人は辞めておいたほうがいいでしょう。
ここでひとつ疑問が出るとすれば「対象者ではないが、話を聞いてくれる人は壁打ち役に適切か?」というものです。
結論から言うと、これはありだと思います。ただ対象者ではないことに気をつければいいだけです。一方、「対象者であるが、話を聞いてくれない人」は、これはそもそもまずいので、違う人に当たった方が良いとなります。これは対象者に対するヒアリングなどにも関係してくるのでさらっと述べるにとどめますが、「釣り好き」であっても、「意見を聞いてくれない」とその意見は使いづらいということです。やや高度ですがその場合は「壁打ち」としての対話ではなく、「釣り好き」の意見を頂くなどテーマを変えた方が適切です。例えば釣り好きの行動や嗜好をサンプルとしてもらうなら、使えると思います。
著者
大橋 弘宜(シゴトクリエイター)
愛知県名古屋市在住。フリーランスのビジネスクリエイター「シゴトクリエイター」として、ビジネスアイデアの創出やリサーチ、PR文などの執筆、壁打ち支援を行う。ビジネスアイデア採択実績は470件以上で、大手広告代理店のビジネスコンペ入賞経験あり。独自に開発した「違和感発想法」を軸に、思考の整理とアイデアの実現を後押ししている。